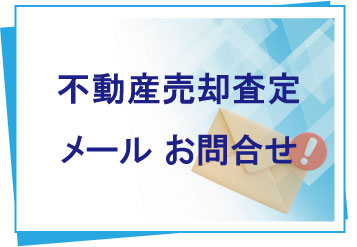分譲マンション管理の未来 - 理事会方式から外部管理方式へ -
現在、日本の分譲マンションを取り巻く環境は、大きく変化しています。高齢化社会の到来、建物の老朽化、そして区分所有者の意識の変化など、従来の管理方法では対応しきれない課題が山積しています。
今回はこうした状況を背景に注目を集める「外部管理者方式」について、そのメリット、デメリット、そして今後の課題について考えていきます。
◆ 理事会方式の限界:高齢化と専門性の壁 ♦
- 深刻化する「役員のなり手不足」
区分所有者の高齢化や多忙化により、理事会役員のなり手が不足するケースが急増しています。マンション管理は責任の負担が大きく、時間の負担も少なくありません。特に大規模修繕工事などの際には専門的な知識が求められ、負担はさらに大きくなります。 - 専門知識の不足と意思決定の遅れ
大規模修繕工事や法改正への対応など、マンション管理は専門的な知識を必要とする複雑な業務が増えています。理事会メンバー全員がそのような高度な専門知識を持つことは難しいのが現実です。そのため、迅速な意思決定が難しく、対応が遅れるケースも少なくありません。 - 非居住者の増加
所有する部屋を賃貸に出したり、空室のまま放置したりする非居住者が増えることで、管理組合の意思決定に影響が出る場合があります。
■ 外部管理者方式:専門家による管理運営 ■
これらの課題を解決する手段として注目されているのが「外部管理者方式」です。これは、マンション管理の専門家(管理会社やマンション管理士などの専門家)が管理組合の運営に携わる方式です。そのメリットとデメリットを考えます。
メリット
- 専門性と効率性
マンション管理のプロが運営に関わることで、専門的な知識や経験に基づいた効率的な管理運営が期待できます。迅速な意思決定が可能になって、すばやい対応が必要な事態にも対処できます。 - 役員負担の軽減
専門家に業務を委託することで、区分所有者の時間と労力の負担が大幅に軽減します。理事会運営に割く時間を他の活動に充てることができるようになります。 - なり手不足問題の解消
専門家が管理運営を担うことで、理事会役員のなり手不足問題の解消に繋がります。
デメリット
- 費用増加
専門家への委託費用が発生するため、管理費負担が増加します。 - 専門家への依存と管理組合の関与低下
専門家に業務を委託することで、区分所有者のマンション管理への関心が薄れる可能性があります。専門家への依存度が高まりすぎると、問題発生時の対応が難しくなる可能性も懸念されます。 - 利益相反(りえきそうはん)リスク
専門家と管理組合との間で、ある行為によって一方の利益が大きくなる一方で、他方の利益が損なわれる状況(利益相反)が発生する可能性があります。透明性のある契約と、適切なチェック体制が不可欠です。 - 元に戻すことの困難さ
一旦外部管理者方式を採用すると、外部管理者への依存度が強くなってしまうため、従来の理事会方式に戻すことができなくなることも考えられます。
管理組合としては、これらの点について、メリットとデメリットを比較検討し、また費用対効果を慎重に判断する必要があると思います。


お子様へ贈る 今月のおすすめ絵本(読物)
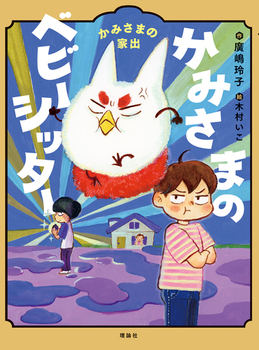
かみさまのベビーシッター
-かみさまの家出-
作:廣嶋 玲子
絵:木村 いこ
出版社:理論社
幸介の家には守り神のボンテンがいます。ボンテンは甘えん坊でわがままで世話がかかりますが、幸介はボンテンが大好きで、ボンテンも幸介が大好きでした。ある日、クラスメートの守り神が、なんでも願いを叶えてくれると聞いて、幸介は羨ましく思ってしまいました。ボンテンのことが大好きな気持ちとわがままでにくらしい気持ちが心の中でぶつかり、気持ちがヘトヘトになっていました。

編集後記
「外部管理者方式」は理事会の業務を軽減し、マンション管理のプロによる高いレベルの運営が期待できる方式です。しかも、従来の「理事会運営方式」と違って、よりスピーディーな意思決定による運営も期待できます。
しかしその一方で、専門家への報酬の支払い分の管理費負担の増加や、管理組合と管理者との利益相反に対する注意が必要になるなど、デメリットも指摘されています。
とはいえ「外部管理者方式」は、居住者高齢化に伴う「役員のなり手不足」の問題を解消する一助となることは間違いないでしょう。しかし、ここで忘れてはならないことがあります。それはマンションは区分所有者全員で管理していくものだということです。
「外部管理者方式」を採用したからといって、何もしなくてもよくなるのではありません。今後ますますマンションの築年数が経過し、同時に居住者の高齢化も進んでいく中で、このことは覚えておかなければならないと思います。